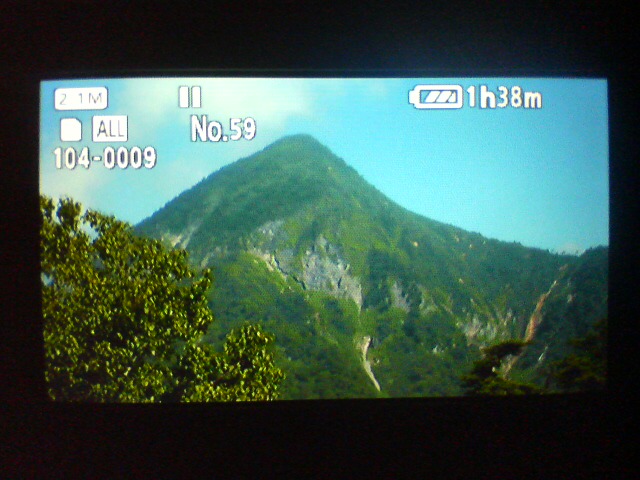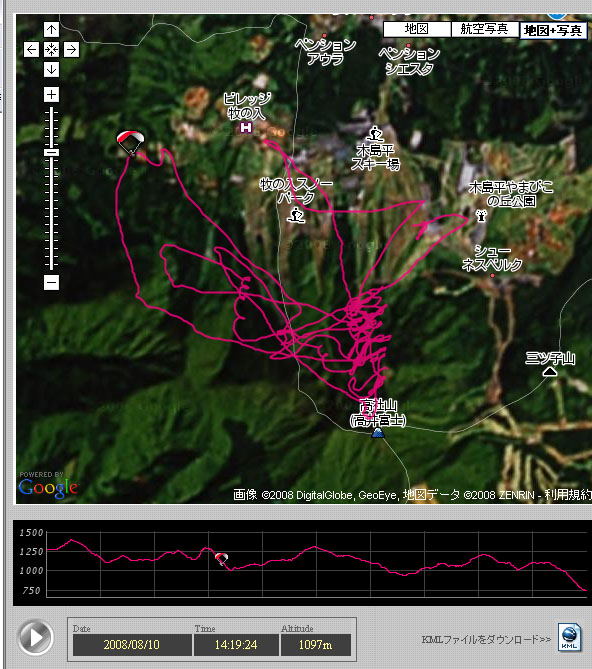パウダーガイド社本社からの富士山
7月10~11日
15時に北口本宮富士浅間神社に、神保町カレーの会の面々(伊藤さん、川崎さん、塩浦さん、秋野さん、松倉)の5人が集合。
浅間神社を参拝してから、スバルライン(2000円)で5合目へと上がる。平日とあり、駐車場はガラガラ。
荷造りをして、伊藤さんが荷物を計測。塩浦さん5kg、秋野さん7kgと二人は優秀なパッキング。
伊藤さんが10kg、松倉12kg、川崎さんはカメラなどの装備があるため17kgと重め。
小御岳神社を参拝し、16時50分に出発。
六合目へと向かう途中にはフジハタザオが花を咲かせている。
ダケカンバやカラマツの樹林を抜け、しばらくで登山指導センターのある六合目となる。
一息入れ、ここから森林限界の中を登っていく。
19時半すぎまではヘッドランプなしで歩る。太子館に20時20分に到着。
ここでしばらく休み、21時45分頃、白雲荘に到着。
秋野さん、塩浦さん、松倉の3人は白雲荘に泊まる(素泊まり5500円)。
伊藤さん、川崎さんは少し歩き、ツエルトビバーク。

翌朝2時に起床。身支度を済ませ、2時20分に出発。
白雲荘の小屋の人によれば、1時がここを通過する人のピークだったとのこと。
つまり、ここを1時過ぎに通過できれば、山頂での御来光にちょうど良いようだ。
ヘッドランプをつけてゆっくりとしたペースで登る。
9合目の鳥居を過ぎたあたりで御来光となる。
雲間から一度、太陽を覗かせるが、すぐに雲の中に。それでも、雲海がオレンジ色に染まり、富士の朝を見事に演出。
伊藤さん、川崎さんに遅れ、5時20分に全員が山頂に到着。
山口屋支店で1時間ほど休む。ちなみに缶ココアや缶コーヒー400円、ラーメン800円。
山頂から暑中見舞いを出す(葉書と切手代で1枚250円)。
1時間ほど休み、お鉢めぐりをする。徐々に上空の雲が晴れてきくる。
剣ヶ峰には7時10分に到着。展望台からは南アルプスがよく見えた。
20分ほど休み、7時半に出発。お鉢一周、休憩含め約1時間10分。
少し休み、準備の済んだ者から順次下山。
私は8時20分に下山開始。それぞれのペースで行く。
長い下りはけっこう膝に来る。全員、無事11時30分に五合目に到着。
下山後は「紅富士の湯」で汗を流し、パウダーガイド社の本社で打ち上げ。(レポート=松倉 )
goraiko movie
http://jp.youtube.com/watch?v=cp56qdCUpfY
以下
一般誌紙依頼原稿もと
富士登山の魅力 伊藤フミヒロ(登山家)
毎年、富士山に登るようにしています。自分のカラダの調子や変化がわかります。トレーニングにもなります。なによりも日本一の山頂に立つことは楽しいし、達成感があるのです。先シーズンは、初めて富士山に登るという知人二人と、よく山に行く仲間、計5人で登りました。中高年男性ばかりのグループです。
7月の初旬、富士山には雪渓が残っています。昼過ぎに富士スバルラインの終点(ここが富士吉田口ルートの五合目です)をスタート。5時間ほどかけて八合目の小屋に夕方着きました。ここで夕食をいただき仮眠、夜中の1時には起きて再スタート、真っ暗な中、ヘッドランプを点けて、山頂を目指します。4時には山頂に立ち、御来光を眺めることができました。天気予報を見て行ったのでおおむねよい天気でしたが、御来光ばかりは完璧なものを見るのはむずかしいようです。この日は地平線にうす雲が広がり、雲の中からぼんやりと朝日が昇るという感じで、80点くらいの出来だと思いました。初めて登るという二人は65歳と55歳でしたが、いっしょに行動することができ、日の出を見てとても感激していました。
●高齢者が登る
この夏は富士登山する人が多く、35万人ほどだったと新聞報道されていました。毎年増加傾向とのことです。周辺の様子を見ますと、やはり中高年が圧倒的に多いようです。中高年の登山ブームは今に始まったことではありませんので驚くことはないのですが、富士山では70~90歳くらいの高齢者も多く、山頂の浅間神社には記帳所があって、そこには99歳とか100歳とか、びっくりするような記録がありました。
ちょっと古いデータですが、平成18年度の記録では、70歳以上で富士山に登り、記帳した人は937名、最高齢は100歳1名。90歳代が10名、80歳代は117名となっています。女性の最高齢は93歳となっていました。また81歳の男性で通算366回も登っている人がいるとも書かれていました。高齢であることは富士登山にとって励みでこそあれ、足枷になるようなものではないと思えてきます。私見ですが、登山は老人に向いているスポーツだと思います。こつこつと忍耐強く歩みを続ければ山頂に立つことができる、経験深い老齢者にぴったりの趣味といえるでしょう。
中高年についで目立つのが子供たちです。小学校生くらいの子供がたくさん登っています。親がついていますので、ファミリー登山です。みなさん元気に山頂に立っています。八ヶ岳や北アルプスなどではあまり見られない光景です。
10代、20台の若者が多いのも富士登山の特徴です。実は他の山(前述の八ヶ岳や北アルプスなど)では意外と若者が少ないのが登山界の今日このごろなのです。元気な学生や社会人が最新のアウトドアウエアやシューズでグループで登ってくる光景は見ていて気持ちのよいものです。
富士登山がブームというのはどうやら本当のようです。日本一高い山に登りたいという気分は大方が理解できるものです。富士山は日本一高い山であると同時に日本一大きな山です。山頂の大きさは実際に登ってみないとわかりませんが、爆裂火口のお釜などは恐ろしく壮大なものです。日本一有名な山、富士山はまた間違いなく登山客数でも日本一です。いちばん高くて大きくて有名な山こそが富士山、というわけです。
●どうしてみんなが登るのか
なぜ人が富士山に登るのか。日本一高い山に登りたいから富士山に登るというのでは、答えになっていないようです。日本人は昔からきれいな形の富士山が好きなのだ、と説明する学者もいます。古くから宗教的な遥拝登山の伝統があって(富士講が有名です)それが今も続いているのだ、という人もいます。御来光を見たいからという人は多いようです。半数以上の人が、夜間登山して山頂からの御来光を眺めます。ドラマチックな自然のショーは確かに見るに値する素晴らしいものです。いくつかの理由があって富士山に人がやってくるのですが、私の見聞から想像すると、多くの人は、友人や仲間、家族、親せきと、お祭りに行くよう感じで、富士山に登ってくるのではないか、と思えます。この夏いっしょに登った仲間も「一年に一度はお参りしないとね」などと言っていました。
年寄りが多く、こどもがたくさんいて、若者もいっぱい、と申し上げましたが、それじゃ、みんな多いんじゃないか、と思われる人もいるでしょう。それほどたくさんの人が登っているということなのです。さらに言えば、外国人がまたやたらと多いのが富士登山です。5人に一人は外国人ではないかと思えることもあります。山頂などでは各国語が飛び交い、国際的な雰囲気があふれます。日本人に限らず富士山は人をひきつける魅力があるようです。
富士山に最初に登った外国人はイギリス人です。初代公使のサー・オールコックです。万延元年ですから江戸時代のことです。日本アルプスの父と言われるウエストンは3回も富士山に登っています。春の残雪期の方が上り下りがラクだと言っています。宗教登山でなくスポーツの一環として富士山を登った最初の人たちです。どちらもこのときの登山記を英国で出版していて、翻訳を文庫本で読むことができます。
●富士山の魅力
遠目には端正な山容も近づいてみれば、崖あり谷ありの荒々しい地形であることがわかります。その群を抜いた標高は、息を切らせながら登る人だけが実感できる感覚です。空気が薄いことが身にしみてわかるのです。山頂に立てばその展望に驚きます。伊豆半島から日本海側の山々まで、本州を縦断する眺めを得ることができます。山頂で口をあける巨大なお釜は、そこに立った人にしかその姿を見せることはありません。オンタデ、アザミ、ハタザオなど火山砂礫帯に可憐に咲く草花も、足で歩いて訪れる人だけが発見できる自然の営みです。
自分の足で歩いて山頂に立った人は大きな満足感を味わうことができます。山頂に達したときの「やったー」「登ったよ」など単純な言葉に思いが込められているようです。達成感は喜びにかわり、大きな自信にもつながっていく、と解説している人もいます。
富士登山の魅力は登った人だけが知ることのできるもの。言葉ではうまく言い表せない「サムシング」ということでしょうか。
●登頂のためのアドバイス
富士山に登ってみたい、と思っている方は、富士山に登ることができます。私は登山ガイドではありませんが、長年、富士山に登って、いろいろな方を見て、そう言うことができます。富士山なんか登りたくない、という人はやはり登れないでしょう。「登りたい!」というモチベーションが基本なのです。あとはいかにラクに登るのか、というコツだけ知っておけばよいでしょう。
そのコツもまたシンプルなものです。それは、できるだけゆっくり登る、ということ。小さい歩幅で時間をかけて登ること、それが富士登山の秘訣です。それから、天気のよい日に登ること、できれば週末やお盆などの混雑時を避けるのが幸福な富士登山を達成するもうひとつのコツと、当たり前のことですが、付け加えたいと思います。