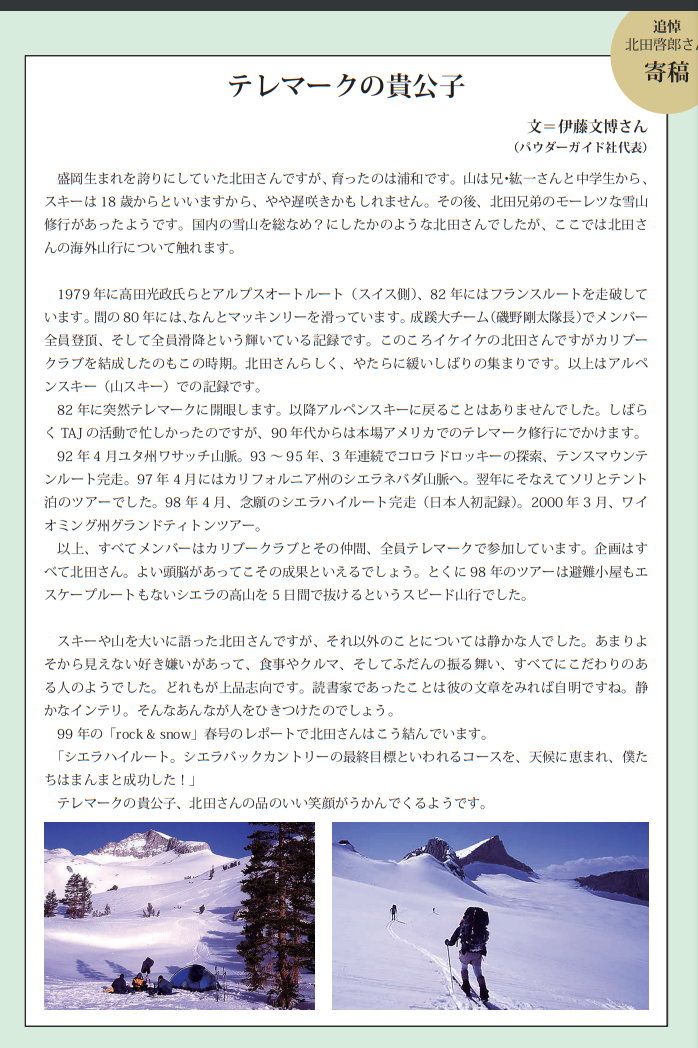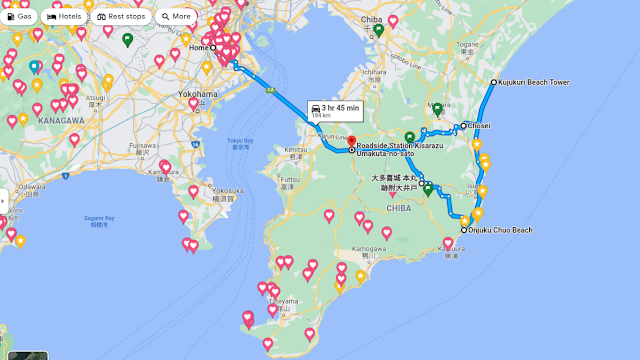ヒマラヤの写真をみていたらなんだか二人の名前が浮かんだ
1990年代ですが、ヤマケイ社に真面目に務めていたころ、私のデスクの前あたりによくすわっていた人がいました。近藤和美さんと高本信子さんでした。
二人とも登山家で編集のしごともできる人だったので、「岩と雪」や特別号「山岳年鑑」のフリーランス編集者として毎年定期的にやってきていたのです。二人とも楽しい人で私もよく雑談やムダ話をしていました。
直接の仕事のやりとりはありません。山にいっしょに行くわけでももなく飲み屋に行くこともなく、毎日顔をあわせるのでいちおう同僚のような雰囲気だったかもしれません。
近藤さんは日本勤労者山岳連盟の遠征隊でそのころすでにソ連だかロシア、中国方面の高山によく登っていた気鋭だったようです。そのごますますエスカレートして日本を代表する高名なヒマラヤ登山家・遠征隊隊長になりましたが、そのころは活躍始動のころだったのでしょう。
登山歴をみるとまるで鬼のようですが、ふだんは穏やかな方で品のいい紳士でした。あるころから近藤さんの記録と実力がまわりにも知られるようになって「近藤さん凄いですね」と話がおよぶと「いやいや、まそんなもんですよ」と謙遜なのか自慢なのかわからないようなニコニコ顔でこたえてくれたとおもいます。
下の記事にもありますが、小柄で、すでに中高年の域に入っているのに、めっぽう山に強かったという奇跡の人だったようです。そんなセレブ登山家が目の前にいるのに気が付かなかったわたしはぼんくらでした。今80歳だそうですがまだまだ元気に山に登っているようですね。
高本さんは女流登山家としてたくさん記録をもっていて交友も広かった人です。日本山岳会の主要メンバーだったのかな。やさしくて親切な人という印象が一番強いのですが、最後の記事にあるようにインドの山旅で事故にあいなくなりました。青山の自宅の葬儀に参列しましたが、たいへんなお嬢さんだったことをしりました。たくさんの人が訪れていておどろきました。
ちょっとヒマラヤのことを考えていたところ二人の名前が浮かんできましたのでネットで調べてみたというわけです。なつかしい。
しかしそれにしても近藤さんの記録は人間離れしていて恐ろしいくらいですね。8000m峰登頂数では日本で2番めとか。遅咲きの登山家としても有名らしい。世界でも珍しいのではないでしょうか。
伊藤文博記 2022年3月記
●
https://blog.goo.ne.jp/repu/e/855c0f930a0ab4d3b2ca07e533699b16
より拝借
高所登山家、近藤和美さん
2009年11月30日 | 山のいろいろ
11月28~29日に千葉市で開かれた労山全国登山集会で、登山家近藤和美(かずよし)さんにお会いしました。
近藤さんは日本を代表する高所登山家で、世界の8000m峰に挑戦を続けています。
登頂を果たしたのは次の8座です
シシャパンマ中央峰(8027m) 1994年 無酸素登頂
ダウラギリ(8167m) 1995年 無酸素登頂
チョモランマ(8848m) 1998年 登頂
ナンガパルバット(8126m) 1999年 無酸素登頂
ブロードピーク(8047m) 2000年 無酸素登頂
K2(8611m) 2000年 無酸素登頂
ガッシャーブルム2峰(8035m) 2003年 無酸素登頂
マナスル(8163m) 2009年 登頂
山頂まで至らなかったものとしても、以下のものに挑戦していらっしゃいます。
ローツェ(8516m) 1997年
ガッシャーブルム1峰(8068m) 2005年
マカルー(8463m) 2008年
他にも6000m以上の山に60回以上登った経験(アコンカグアなど)をお持ちです。
「ヤマケイ登山学校:冬山」(山と渓谷社)や「谷川岳」(昭文社)などの著者でもあります。
私は実際にお会いするまで、「鉄の男」というイメージを持っていました。
しかし実際の近藤さんは、小柄で優しい笑顔が似合う方
驚いたのは、手と足の指20本は完璧にそろっています! 高所登山ではしばしば凍傷で指を失くしてしまうので、これはオドロキでした。
実際に指に触らせていただきましたが、柔らかい指でしたよ~
どうして高所に強いのかお尋ねしたところ、「自分でも理由はわからないけど強い」とのことでした。
●
http://blog.livedoor.jp/buntak2/archives/51620733.html
より拝借
20080827近藤和美マカルー登頂報告会
タイトル20080827マカルー報告02近藤
今春、マカルー峰(8463m)に登頂した労山隊の報告があるという近藤さんからの連絡を受け、登頂者:橋本久さんに久しぶり(1998年のマカルー以来)に会えるのではないか?と僅かばかりの期待を持って、東京飯田橋の労山事務所へ出かけてみた。
仕事を早めに終え、上野・秋葉原まわりで飯田橋へ。そこから徒歩10分ほどで事務所に到着。早めに集まっていた人たちへ、アンデスのフォルクローレの楽器演奏をしていた。
近藤さんに挨拶したが、「盛岡からは来ないよ!?」の一言で、橋本さんは現れないことを確認。頂上へのルート取りが一番の関心事になる。
今日は、正式には 労山全国連盟メディア局:主催の「登山時報第1回文化講演会」-新しい読者を増やすための交流と講演の集い-で、
講師:近藤和美さん(2008全国連盟八千m峰登山隊・隊長)
演目:「世界第5位の難峰マカルーに登頂」
と言うものであった。
よって、東京近郊の「登山時報」購読者が集まったもので、期待していた隊員や現役のクライマーが集まるというものではなかった。
しかし、98年に埼玉と同時期に登山していた岩手の山童子隊の橋本さんが登頂したというので、関心大であった。
まず、近藤隊長から今回の遠征の経緯が話され、スライドを上映しながら遠征隊の様子を話された。只、アタックに関しては「橋本・波多野2氏」が登頂者の為、二人の話を聞いた隊長の報告だった。
1.労山8000m挑戦からマカルーまで
94年、労山隊として初めて8000m峰に挑戦した。最初は、シシャパンマに挑戦し中央峰(8008m)に登頂。
以来、08年まで15年間、計12回の遠征があり、8000m峰11座に登頂。
今年08年は、チベットのチョーオユーとシシャパンマの2座連続登頂を目指した。メンバーは橋本氏以外は、シシャパンマ、チョーオユーなら大丈夫と見て参加。
しかし、北京オリンピックの聖火リレーの関係から、チョモランマは入山禁止。(それもチベット側のみならずネパール側も一時禁止となった。)チョモランマ近くのチョーオユーは、シシャパンマ登頂後にすれば登れるのでは?、と取り敢えず3/18と3/24に出発。
まずは予定通り、ランタン谷のヤラピーク(5520m)で高度順応登山。折角だからとゴザインクンドへも立ち寄ったという。ヤラピークの下4700mのヤラカルカにBCを設置し、3日間滞在し2回登頂して順応終了。
4/8カトマンズに返って来るもチベット情勢は好転せず、転進を考える。
①前回、7500mまで行っているマナスル、
②今春、15隊入るという情報のあるマカルー
のどちらか?という選択肢。
①は、隊長も記憶が鮮明で登頂を逃したピークなので再挑戦しやすい。
②は、隊員の橋本氏が10年前に登頂を試み、目前で断念した山。事前に資料を持ってくるように指示してあった。また、めったに15隊も入山しない山なので、登頂のチャンス。橋本氏の雪辱戦ともなる。
他の隊員にとっては厳しいかも知れないが・・・「隊長の判断にまかせる」という橋本隊員以下の隊員の言葉で、「マカルー」に転進することに決定。
幸い今回利用している「ボチボチトレック」(福岡の渡刈氏?が出資、グルン族の○○がオーナー)では、今春3つの8000m峰を扱っている。
①マナスルの倉岡隊、②マカルーのスペイン隊、③同じくマカルーになった労山隊で、スペイン隊の隊長:エマニエル?氏は、何度かBCで一緒になっていて友好的。隊員の河合氏がスペイン語が話せ、好条件。
2.カトマンズからマカルー登頂まで
4/18隊荷2.4tと共にツムリンタールへ移動。隊員は飛行機。隊荷は陸路。ここから荷物をジープに積み替えて、ボーテパスまで運び、そこからキャラバン開始。2回の大きな上り下りを経て、
4/27、チャゴ氷河末端のBC(5700m)に到着。前回山童子隊のABCだったところ(現在のBCになっている)。統計によると計23パーティが集結していたという。
<<行動日誌>>
4/30 仮C1(6350m:98のC1)往復。
5/7 C1(6650m:98のC2)泊
5/8-9 全員が7100m-7300mへ往復。
5/13 C2(7550m:マカルー・ラの上部)到着。
5/18 橋本・波多野アタック開始のためBC出発。
5/20 最終C3(7850m)に入り、21:30アタック開始。
5/21 5:40登頂成功。後BC帰着。2次隊はC2入りを目指したが断念。その後天気が崩れる。
5/26 BC撤収。ヤンレ・カルカ(3500m)まで降りる。
5/29 ヤンレカルカよりヘリにてカトマンズ到着。(天候待ち1日)
6/2 帰国
<<ルート等の状況など>>
・最終キャンプ(C3=通常のC4)は、北西稜上の7850m。テント3張りがやっと張れる広さ。張り捨てられていたテントを借用。
・夜9:30(21:30)スタートは早すぎたが、この時期の天気が不安定で、昼前から崩れていたので、崩れる前に安全圏に下山したかった為、早い出発を選ぶ。幸い、ルートを知っているサーダーが先行したため、難しいガリー入口も素早く発見。最後は夜明けを待って山頂を踏む。
・C3から雪壁のユマーリング。酸素流量毎分2.5L。最初の1時間は、5-6ピッチのユマーリング。
・FIXが無くなってからは、クレバス帯を避けるために雪田を大きく右に回り込みながら登る。モナカ雪。
・頂上へ抜けるルンゼは、頂上直下のルンゼ(98年失敗)ではなく、はるか下方の、頂上の岩稜帯から発生している左上方のルンゼを目指す。
・クレバス帯を3時間程かけて登り、ルンゼ末端にあるFIXロープを見つけて、それを登る。
・FIXは5-6ピッチ。上部稜線に近づくと無くなる。
・上部ほど岩の露出が多く、雪も不安定。
・やっと岩場を登りきると、目前に頂上が確認出来る。1時間ほど待つ。
・最後の登攀=狭い雪稜をFIXを頼りに3ピッチ、100mほどトラバースして到着。
・C1~C2間は、20ピッチ以上のFIX。(98年とはルートが違う。)
<<以上橋本氏の報告より>>
3.他
・隊員7人中、登頂者2名はどうだったか?
・5700mのBCは、50歳代には疲れが取れない。(世界一高いBC)
・労山の8000m登頂峰は11座。残るは、チョーオユー(2009年春)、カンチェンジュンガ、アンナプルナのみだが、難しいところが残っている。
◆久しぶりの報告会に参加。それもマカルーだったので興味しんしんであったが、残念ながら登頂者の話が聞けず残念。写真も数枚しかなく、詳しく確認できなかった。
今年はチョモランマやエベレストからの転進組が大挙してマカルーに押しかけたようで、計23隊(パーティ)がマカルーをねらったという。それも殆どが北西稜。
報告にもあるように、頂上まで殆どFIXロープが張り巡らされたようだ。
10年前のマカルーを思い出すと、隔世の感がする。
●
ウイキペディアより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%97%A4%E5%92%8C%E7%BE%8E_(%E7%99%BB%E5%B1%B1%E5%AE%B6)
近藤 和美
(こんどう かずよし)
生誕 1941年11月22日(80歳)
愛知県名古屋市
国籍 日本の旗 日本
職業 山岳ガイド
著名な実績 8000メートル峰9座登頂
受賞 スノーレオパード賞(1989)[1]
概要
1941年11月22日、愛知県名古屋市に生まれる。17歳で上京就職、1976年に17年間勤めた会社を退職。日本勤労者山岳連盟で「山と仲間」編集長を務めたのち、1984年よりフリーランサーとなり、山岳雑誌、山岳書籍の編集に従事、1987年登山ガイドとして独立。山と高原地図(昭文社)「谷川岳」の調査執筆を長年請け負った。
1972年31歳より海外登山をはじめ、42歳で7000m峰初登頂、1989年旧ソ連邦に属する7,000m峰5峰(イスモイルソモニ,ポベーダ,レーニン,ハンテングリ,コルジェネフスカ)を完登した者に贈られるスノーレオパード賞を獲得した[1]。
1992年50歳で8000m峰初登頂(ダウラギリ)、その後も8000m峰に挑戦し続け、2011年69歳でローツェに登頂し、8000m峰9座に登頂(うち5座無酸素登頂)した。たいへん遅咲きの登山家である。8000メートル峰9座登頂は、名塚秀二、田辺治、山田昇と共に、全14座達成の竹内洋岳に次ぐ日本人2位の記録[2][3]。
日本勤労者山岳連盟海外委員、日本ヒマラヤ協会会員、日本山岳協会国際部海外常任委員、パミール中央アジア研究会理事。
エピソード
1989年8月、近藤和美を含む日本勤労者山岳連盟隊はハン・テングリへ遠征を行っていた。この遠征は高所登山の経験者養成の目的も兼ねていた。参加者の1人の北沢真一は講師役として、ハン・テングリを数度登頂していたが、8月14日、下山中に滑落死してしまう。翌年、ハン・テングリの6,400m付近に慰霊碑が設置された。『世界の名峰グレートサミッツ』「ハン・テングリ」の回の制作に携わっていた貫田宗男がこの慰霊碑を知り、近藤和美に取材を行った。この慰霊碑は平出和也によって撮影され、北沢真一のエピソードと共に、2013年1月に放映された番組において取り上げられた[4]。
経歴
1941年11月22日 - 愛知県名古屋市に生まれる。
1986年8月3日 - イスモイル・ソモニ峰(7,495m/タジキスタン)登頂。
1986年8月 - コルジェネフスカ峰(7,105m/タジキスタン)登頂。
1986年 - レーニン峰(7,134m/タジキスタン)登頂。
1989年 - ハン・テングリ(7,010m/キルギス)登頂。
1989年 - ポベーダ山(7,439m/キルギス)登頂。
1989年 - スノーレオパード賞獲得(同年に日本人として初獲得した小西浩文に引き続き日本人2人目)。
1992年9月20日 - チョ・オユー(8,201m/チベット)無酸素登頂。(木本哲,八橋秀樹等11名)
1995年10月6日 - ダウラギリ(8,167m/ネパール)無酸素登頂。(林孝治,桑原巌,成崎公生,澤田実,武田澄人等8名)
1997年5月10日 - リスム(未踏峰/7,050m/チベット)初登頂。
1998年5月22日 - エベレスト(8,848m/ネパール)登頂。(倉橋秀都,佐藤賢,永田幸一,坂本正治,橋本久,矢野利明,川原慶紀8名)
1999年7月29日 - ナンガ・パルバット(8,126m/パキスタン)無酸素登頂。(倉橋秀都,清野嘉樹等5名)
2000年7月30日 - ブロードピーク(8,051m/パキスタン)無酸素登頂。(倉橋秀都,矢野利明,松本政英4名)
2003年8月1日 - ガッシャーブルムII峰(8,034m/パキスタン)無酸素登頂。(橋本久,飯塚公知,上野幸人4名)
2006年10月26日 - ナンパイゴスム[南峰](未踏峰/7,240m/ネパール)初登頂[5]
2009年5月19日 - マナスル(8,163m/ネパール)登頂[6]。
2010年5月17日 - シシャパンマ(8,027m/チベット)登頂。シシャパンマ最年長登頂更新(68歳176日)[7]。
2010年11月3日 - チュルー最東峰(6,038m/ネパール)登頂。
2010年11月8日 - チュルー南東峰(6,429m/ネパール)登頂。
2011年5月20日 - ローツェ(8,516m/ネパール)登頂[8]。
著書
雨宮節・宮下正次・近藤和美著「記録 魅惑の氷壁」(1979/8,ユニ出版)
小宮昌平・近藤和美編「山 生きる・学ぶ・探る」(1986/2,大月書店) ISBN 978-4272610051
近藤和美調査執筆「谷川岳・苗場山・武尊岳 1994 山と高原地図28」(1994/1,昭文社)
近藤和美調査執筆「谷川岳・苗場山・武尊山 1996 山と高原地図28」(1996/1,昭文社) ISBN 978-4398750280
近藤和美著「冬山」(1996/12,山と渓谷社) ISBN 978-4635041805
近藤和美調査執筆「谷川岳・苗場山・武尊山 2001 山と高原地図16」(2001/1,昭文社) ISBN 978-4398752284
近藤和美調査執筆「谷川岳・苗場山・武尊山 2004 山と高原地図16」(2004/9,昭文社) ISBN 978-4398754165
近藤和美・高橋修調査執筆「谷川岳・苗場山・武尊山 2006 山と高原地図16」(2006/1,昭文社) ISBN 978-4398754165
●
高本信子さんのこと
以下 日本山岳会のページから拝借
https://jac1.or.jp/images/media/rokusoukai/ryokuso-No161.pdf
~《寄稿/投稿》~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私が敬愛する長老(その5)
関塚 貞亨
敬愛する長老たちは、ある方から『山岳』に投稿して広く会員に読んでもらうように提案があっ
て、33人を書いたのだが、長すぎるという指摘もあり5人を削り、28人を『山岳』に投稿した。
採用されれば『山岳』に載るので、削減した5人を緑爽会の会報に掲載してもらうことにしまし(村
山雅美氏は160号に掲載済みにつき今号では4人)
山岳会の佳人
◎高本信子(1941年~1992年)
私が入会したときの推薦者は折井健一さんで、山研委員長をしていたので私も委員になった。そ
の時の担当理事が高本さんだった。山岳会に入って初めて晩餐会に出たときに山姥のような人は一
人もいなくて、友禅の訪問着やサリー姿の婦人方がみな優雅な人たちだったのには驚いた記憶があ
るが、初めて身近に接した高本さんも優雅な佳人で雑誌「岩と雪」の編集をしている方だと他の人
から聞いた。
山研の理事を二年で務められた後は婦人懇談会の担当理事になり、印度ケダルナートのドーム登
頂計画の隊長なった。女子の登攀隊の中にはサミッターがサポートした隊員への感謝を忘れて反感
を買い、ばらばらになって解散する隊の例も知っているが、高本さんの隊は皆仲良しで帰国後も交
際が続いた。不幸にもインドに旅行中、乗用車に大きな岩が直撃して亡くなられた。『山岳』第8
8年に追悼記を書いた大久保晴美さんも2018年に亡くなられた。
ドームに遠征する前に私の描いた霞沢岳の絵を気に入って所望され、高本さんからは、これから
登るドームの額入りの写真を頂いた。亡くなられた後、私は音痴だが琵琶湖周航の歌の一節「仏の
み手に抱かれて…」を歌いご冥福を祈った。